はこだてわいん×ハコダテアンチョビ
~生産者対談~
地域の生産者が思い描く道南の未来

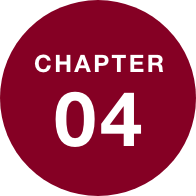 ワインとアンチョビから考える道南食文化の未来
ワインとアンチョビから考える道南食文化の未来

―地域に根ざした商品作りについて、今後の展望を聞かせてください。
- 齊藤さん
- ハコダテアンチョビとしては、世界を目指したいというのが大きな夢です。マイワシで作ったアンチョビは他にありませんし、世界でも十分に通用する味になったと思うので。
もうひとつは、アンチョビを作った際に出る魚醬の活用を考えています。いわゆるナンプラーというやつですね。これを商品にしたり、メニューを開発するだけでなく、ミネラルやアミノ酸を多く含んでいるので、農業に活用するなどの方法もあるのかなと。そういう新しい展開もできたらいいなと思っています。
あとは、ハコダテアンチョビの仕組みを、他の地域でも展開できないかなと考えています。その地域でとれるのに値段がつかないものを、その地域の加工業者さんで商品化して、その地域の就労支援施設でパッケージしてもらい、その地域で販売するという仕組みを広げていけたらなと。

―確かに、各地でフードロス問題はあるでしょうし、生産者、加工業者、就労支援施設の方が提携すれば、どこでも再現可能な仕組みですもんね。
- 渡辺さん
- 私たちの業界について言うと、道南は今、ワインの産地化が急速に進んでいるんです。道南でブドウを育て、地域に根ざしたワイン作りをされている方がいたり、フランスから有名なワイナリーが進出してきている状況で、おそらく数年のうちにもっと作り手が増えていくと思われます。そのなかでずっと道南でワインを作り続けてきた我々がやるべきことは、地域の食材と一緒に楽しんでいただくことだと考えているんですよね。
我々が一番求められるのは「どうしたら美味しくワインが飲めるのか」という提案なんです。であれば、家庭で再現できるものでワインに合う食材も一緒に紹介しましょうと。それは地域貢献にも繋がるでしょうし、何よりはこだてわいんを一番美味しく飲んでもらえる方法でもあると思うので。今後の展望としては、そういったことを考えています。
―はこだてわいんさんは、自社の畑でブドウも育てていますよね。そちらは今、どういう状況なのでしょうか?
- 渡辺さん
- 今は足掛け7年目で、何とか1トンくらいの収穫ができるようになりました。面積は1.7ヘクタールで、かの有名なロマネ・コンティと同じくらいの広さです。そこで段階的にシャルドネやカベルネ・ソーヴィニヨンを植えています。

自社農場(七飯町)収穫間近のシャルドネ 写真提供:はこだてわいん
- 渡辺さん
- カベルネ・ソーヴィニヨンは、まだ北海道でほとんど植えられていなくて、今は岩手か青森くらいまでが北限とされているんですよね。ただ、温暖化の影響で産地が移り変わってきているので、数年後には函館のカベルネも世の中に認められるようになるかもしれません。まだまだ実験段階ではあるのですが、この辺りの農家さんにも一緒にブドウを作ってもらえるようになったらいいなと思っています。
―そういう動きが生まれると、道南のワインはますます盛り上がっていきそうですね。
- 渡辺さん
- そうですね。うちの畑で採れたブドウのワインは、去年と今年で1回ずつ出して、周囲からも期待の声をいただいております。ただ、まだまだ我々の望むものではないので、試行錯誤を続けているところです。ブドウの栽培にもワインの醸造にも時間がかかるので、気の長いビジネスなんですよね。
―道南にワイナリーが増えているという状況については、どう捉えていますか?
- 渡辺さん
- ひとつは危機感ですね。だけど、一方でチャンスだとも思っています。やはり産地形成されないと、お客様には来ていただけないので。
山梨のようにワイン作りの歴史が長い地域では、メーカー同士が非常にフレンドリーで、技術協力をしたり、悩みを打ち明けたりという関係性を築いています。我々も横の繋がりを大切にして、みんなで成功できるのが理想ですね。ワイナリーごとに美味しいワインがあって、それを巡るツアーなんかいいじゃないですか。ワインをテーマに道南旅行をしてくれるような方が増えると嬉しいなと思っています。

―最後に、道南に対する想いを聞かせてください。これから道南というエリアが、どのようになっていってほしいと思っていますか?
- 齊藤さん
- 東京でもそれなりの食材を見てきたし、他の地域の食材にも目を向けてきたんですけど、道南ってかなりバラエティーに富んだものが手に入る土地なんですよね。本当に何でも手に入る土地だと思います。東京も何でも手に入りますが、あれは全国から食材が集まっている状態じゃないですか。だから、財力があれば何でも手に入る土地なんですよね。
でも、道南は四季を通していい食材が適正価格で手に入るので、料理人としては本当にパラダイスだと思います。今まであまり日の当たらなかったような食材にも、料理を通して価値をつけられる可能性もあるじゃないですか。100円にしかならなかったものが1000円で売れるようになったら、その分を次のチャレンジに回していけるので、そういう取り組みを増やしていきたいですね。
―食材が豊富なだけでなく、そういったチャレンジができる余地もあると。料理人としては絶好のフィールドなんですね。
- 齊藤さん
- 本当にそう思います。その時期に出てきた食材を使えば、価格を安定させられるし、一番美味しい。夏の食材を冬に出そうとするからおかしなことになってしまうんですよ。その時期にとれた美味しい食材を、大事に調理して提案すれば、お客さんは喜んでくれますよね。だから、四季の移ろいで手に入る食材が変わる最高の遊び場だと思っています。

―ハコダテアンチョビの生産を通じて地域の課題も見えてきたと思いますが、道南がもっとこうなっていったらいいなというイメージはありますか?
- 齊藤さん
- 道南というと、やはり函館のイメージが強いじゃないですか。でも、最近は他の町を訪れる機会も増えて、グルメやアクティビティなど、それぞれに魅力を感じています。なので、外から来る方はもちろんですけど、函館の人が近郊の町を訪れるような流れが生まれるといいなと。シェフというのは、そういうきっかけを作れる職種のひとつだと思うので、今までになかった提案をしていきたいですね。

- 渡辺さん
-
齊藤さんがおっしゃったように、道南は本当に食が豊かなエリアですよね。以前、函館市役所さんが、「函館を日本のサンセバスチャンにする」と⾔ってたんですよ。美⾷の街にするんだって。そういう可能性が本当にある街だと思います。
優れたワインを作るために必要な要素は3つあると言われていて、いい原料と、いい作り手と、もうひとつはいい市場なんです。函館は、食を求めてくるお客様がいっぱいいらっしゃる土地じゃないですか。地のものを食べたいというニーズは多いと思うので、そこに我々もいたいなと思っています。
―旅行先では、その土地のものを食べたいですもんね。観光の街である函館は、そういったニーズも大きいってことですね。
- 渡辺さん
- そうですね。一方で、幸福度の調査では函館はいつも低い順位ですよね。それは本当に問題だと思うので、産業の発展や雇用の創出によって、少しでも前向きになっていったらいいなと思っています。地域貢献ということを考えたときには、やはり住んでいる人の幸せが一番重要ですから。

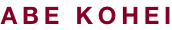 阿部 光平
阿部 光平
インタビュアー
北海道函館市生まれ。大学卒業を機に、5大陸を巡る世界一周の旅に出発。帰国後、フリーライターとして旅行誌等で執筆活動を始める。現在は雑誌やウェブ媒体で、旅行、音楽、企業PRなど様々なジャンルの取材・記事作成を行っている。東京で子育てをするなかで移住を考えるようになり、仲間と共にローカルメディア『IN&OUT –ハコダテとヒト–』を設立。2021年3月に函館へUターンをした。
Twitter
 あらいあん
あらいあん
カメラマン
1967年、函館市生まれ。本名は荒井藤香。
ライフワークとして函館、道南の風景と人々の写真を撮るひと。インタビュー撮影やウェディングフォト、第一次産業や店舗、会社のプロモーション撮影など心ときめくモノはなんでも撮る。将来は函館を代表する有名なおばあちゃんフォトグラファーを目指している。






